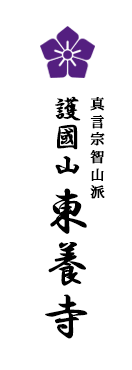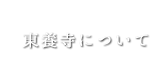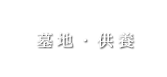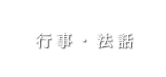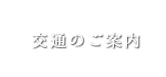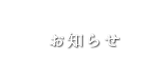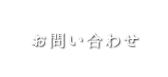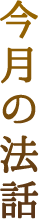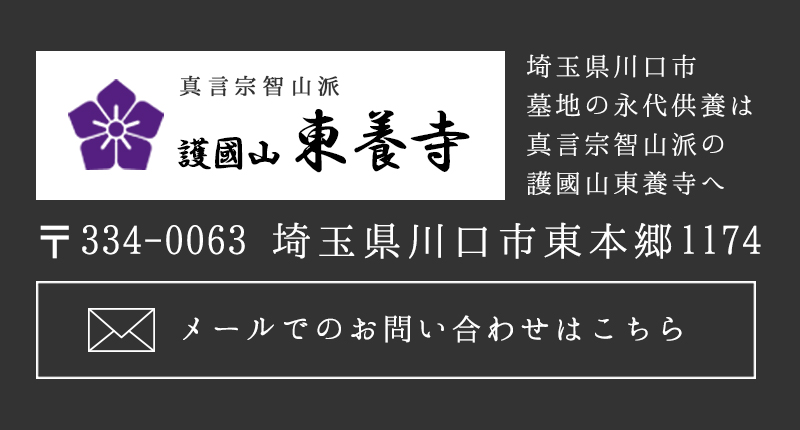慢心
春のお彼岸に際しましては、多くの檀信徒様等のご来寺をいただき、ありがとうございました。墓所も色とりどりの供花で埋まり、皆様のご先祖様もさぞ喜ばれたかと思います。
我慢。現代では「怒りや悲しみに耐え、辛抱する、忍ぶ」といった意味合いで用いられる言葉ですが、もともとは四慢(四つの慢心)のひとつで、「自分に執着した結果、自分を高く、他者を低く見る心」という意味でした。
四慢とは倶舎論(くしゃろん)などの教典に書かれている、我慢、増上慢(ぞうじょうまん)、卑慢(ひまん)、邪慢(じゃまん)の四種類の慢心のことです。増上慢とは、悟っていないのに悟ったと思い込み、おごり高ぶる心。卑慢とは、非常に優れている人を見ても自分はその人より少ししか劣っていないと思う心、邪慢とは、間違った行いを正しいと思い込み、自分は徳が無いのに徳があると思い込む心、です。
いずれの慢心も、言葉を目にしただけで気分が悪くなるような心持ちです。「自分はこうではないし、こうあってはならないし、これからもこうならないようにしよう」と皆さま思われるのではないでしょうか。
しかしながら昨今、これらの「慢心」にあてはまるとしか思えない言動を、インターネットでも現実社会でも目にすることが多くなりました。
インターネット、特にSNSの世界では「自分の思っていることが唯一無二の真実である」と信じて疑わないような人たちが自説を披歴しています。目に入ってくるのは、別の意見を述べる人を頭から否定したり、誰かを叩いている人の後ろから一緒になって同じ相手を叩いたりする風潮です。
そして現実世界では、例えばあの超大国の大統領などはその代表的な存在といえるのではないでしょうか(個人の見解です)。「各国の首脳が我々にすり寄り、『なんでもしますから』と懇願してくる」「FRBのパウエル議長の判断はいつも遅すぎ、間違っている」毎日のようにこんな発言が報じられています。
こんな世の中は間違っている、と言うつもりはありませんが、世の中が良い方向に向かって動いている、とは言えないとは感じます。公に何かを言うときには、一度立ち止まって深呼吸し、「自分の中に慢心は生じていないだろうか」と省みてみる、まず我々ひとりひとりが、そんなことを心がける、そこから始めてみてはどうでしょうか。そんなことを考えています。